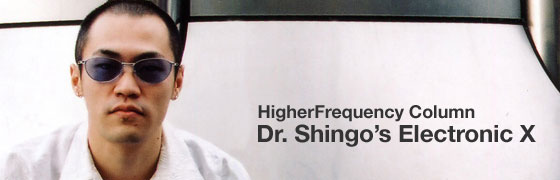Text & Interview : Dr. Shingo
みなさんこんにちは。ドクターシンゴです。
とうとうこの「ドクターシンゴのエレクトロニックX」も連載10回目となりました!
足がけ2年以上もやっているのにまだ10回目!と振り返っている僕自身が驚いています。
さて、みなさんご存知の通り、昨年より僕のレーベル「HIGHLAND」が始動、着々とリリースを
hrfq.com 内で行っています。デモテープも相変わらず大募集中ですが、その大募集中のデモテープの
中からキラリと光る宝石の原石を発見しました。彼の名は gben。 "odia"EP が絶賛発売中ですので、
まだチェックされていない方は是非聞いてみてください。何とリリースから一週間は techno のジャンルに
限らず All の中でも1位にランキングされる快挙を成し遂げました。おめでとうございます!
将来が非常に楽しみなアーティストです。
今後都内でライブ等を行っていくとの事なので、フライヤーで名前を見つけたら足を運んでみて下さいね。
デモテープはもちろん今現在も募集中です。 「 俺の方が/私の方がもっと凄いトラック作ってる yo!」
という兵の皆さん、どしどし送って下さい。
デモ曲送付先
〒153-0043 東京都目黒区東山 3-7-3 VIEW 東山 301
hrfq.com 内 Dr.Shingo "HIGHLAND" デモ音源係
さてこのエレクトロニックX,第一回目のモニカ・クルーゼから始まり色々なアーティストのインタビューを
紹介してきました。熱心に読んでくださっている人の中にはお気付きの人もいるでしょう。
そう、質問のパターンが同じなんです。細かい所については個々のアーティストの活動にもよるし、
色々と違いも出てきますが、基本的には同じ流れで質問をしています。どんな生い立ちを過ごしたのか、
プロの DJ になるまでの過程、どんな方法でシーンにその存在をアピールしてきたかなど…。
読み返してみてください。同じでしょ?
これには、このインタビュがこれから DJ / プロデューサーになりたいと思っている人へのテキストになればという
思いが込められています。このミュージシャンの世界には企業の様なマニュアルがありません。
したがってアマチュアミュージシャンがプロフェッショナルになるには、沢山の?マークが存在します。
インタビューに出てくるミュージシャンの過去は、すなわち後進のミュージシャンの道しるべになると思うのです。
親切に「プロの DJ になるにはどうすれば良いか?」なんて事を教えてくれる学校があれば良いのですが、
実際はそうは行きません。狭き門、特殊な職種ゆえに情報も少なく、ある意味 「マニュアル化」 が難しくも
あります。さっき道しるべと言いましたが、その通りにステップを踏めばミュージシャンになれる保障もありません。
では一体これらのインタビューから何を学べるか?それはアーティストの 「情熱」 だと思うのです。
みんな若い時分に音楽に多大な影響を受け、自分の才能を信じ、信念を曲げず、信じた道を歩く…この姿を
見習ってもらえればと思います。 「好きこそ物の上手なれ」 なのです! 僕もインタビューをしながら見習う所が
沢山あります。皆さんも、もっともっと自分を信じて曲を作って DJ いっぱいして、一緒に日本のシーンを
世界にアピールして行こうではありませんか!!
もちろんそれだけではなく、インタビューではアーティストのパーソナリティを紐解いていくという、
読み物としても通じる様構成を心がけています。まあ肩肘張らずにこれからもお付き合い下さい。
連載10回目のご挨拶でした。
2007年最初のゲストインタビューは Joel Mull (ジョエル・ムル)です。イケメンです。
90年後半に一世を風靡したスェディシュ・テクノ・ムーブメントの立役者の一人です。皆さんも、DJ の皆さんも
アダム・ベイヤーに代表されるスゥエディッシュ・テクノにはお世話になった事でしょう。僕がテクノを本格的に
聞き始めたのが99年頃で、DRUM CODE のコンピレーション CD には随分驚きました。
喋り方は非常に温和で、真面目な性格の持ち主です。そして繰り返しますがイケメン。
そんな彼の音楽家としての生い立ち、スェディシュ・テクノ・ムーブメントについて、最近のプロダクションについて
等面白い話を色々と聞く事が出来ました。今回もボリュームたっぷりです。最後までじっくりお楽しみ下さい。
尚、彼の最新アルバムが、名門 HARTHOUSE よりリリースされます。
Joel Mull / The Observer / HartHouse
2007年4月以降の発売 詳しくは www.harthouse.com
こちらもリリースされたら是非聞いてみてくださいね! 最新のテックハウス/クリックサウンドが満載です。
それではインタビューをどうぞ〜〜〜〜〜!
![]()

Dr. Shingo : まず始めにジョエルが音楽を始めたキッカケから聞きたいのですが、プロフィールによると6歳の 頃からピアノを弾き始めたそうですね。それって自分からやりたいと言い出したの?それとも両親から 勧められたの?
Joel Mull : 母親がピアノ教室に行く事を勧めたからなんだけど…どうやら僕が小さい頃から 音楽に興味がある事を発見したみたいなんだ。
Dr. Shingo : それってどんな場面をみたから…?
Joel Mull : う〜ん、なんだか良く分からないけど音楽を聞くのが好きだったり、歌を良く歌っていたみたいなんだ。 そういう場面を見て母親は自分に音楽の才能があると見込んだみたいだね。
Dr. Shingo : それは面白いですね。僕も母親から小さい頃ピアノ教室に行く事を勧められた事があったんです。 同じ様に母親は「この子には音楽の才能がある!」と思わせる場面があったからだそうで、それは 幼稚園のお遊戯の時間に起こったらしいんだけど…。みんなで簡単な歌を歌うでしょ? 大体の子供は音を拾う事が出来なくて、ただ音階がない棒の様な歌しか歌う事が出来なかった。 だけど自分だけはちゃんとピアノの音程に合わせて音を拾う事が出来て、メロディイを正確に 歌う事が出来たそうです。それを見た時にこの子にピアノを習わせようと思ったらしいですよ。 結局女の子ばかりが通うピアノ教室には恥ずかしくて通わなかったけれど。
Joel Mull : 僕の場合もそんな感じだったと思うよ。6歳のときにカシオのキーボードを買ってもらったんだ。 玩具みたいな安い奴で、ドラムのビートとかベースパターンとかがプリセットで入っている奴。 で、そのカシオでラジオから流れる音楽のメロディを真似して弾いて遊ぶんだ。後ね、テープレコーダーに それを録音したりもしたね。自分のラジオ番組を作っていたんだよ(笑)。
Dr. Shingo : ははははは。それって何歳頃の話?
Joel Mull : それは…7歳ぐらいだろうね。キーボード弾いて自分で喋ったのを、ラジカセに突っ込んだマイクで 録音するんだ。でも7歳だから英語とか喋れないでしょ?だから何喋ってるか分からない ”イマジネーション・イングリッシュ”なんだ(笑)。もしかしたらそれが何か物作りに目覚めた きっかけなのかも知れないね。
Dr. Shingo : なるほどね〜(笑)。それは面白い。
Joel Mull : そんな訳で、かなり小さい頃からエレクトロニック・ミュージックを聞いていた。 父親が凄いレコードコレクターでね、クラフトワークはもちろん、パンクロックとか色々と聞いていたんだ。 そんな自分を見て母親が、「そんなに音楽に興味があるなら、ピアノを習いに行きなさい」ってな感じで ピアノを習いに行き始めた訳。だけど退屈でね…。本当に行くのが嫌だったよ。 それから小学校2年生…9歳ぐらいかな、学校に行くのが嫌で嫌でしょうがなくってね。じっと座ってられないんだ。 そこで違う学校に行く事になったんだけど…。
Dr. Shingo : それがプロフィールにある、10歳の頃音楽学校に行く、と言う奴?
Joel Mull : そう。そこではボイスクワイヤー(合唱団の様な物)という科に入ってね。声も良い方だったから、 合唱団のリーダーにはよく、「もっと身を入れてやってみなよ」なんて言われたりもしたね。
Dr. Shingo : 音楽学校での勉強ではクラッシックが中心?ポップとかモダンな音楽は勉強しなかった?
Joel Mull : クラッシックが中心だね。週に8時間位は音楽の勉強、後の時間は歌のレッスンや合唱の練習をしたりしたよ。
Dr. Shingo : スゥエーデンでそういう音楽学校に通うって事は、入学した人達はプロのミュージシャンを目指したのですか? クラッシックのオーケストラに入る為とか…?
Joel Mull : まあそういう人もいただろうね。だけど全員がプロの音楽家志望と言うより、そこから音楽に関係する仕事に就くためという 目的の人もいたね。入学するには幾つかの楽典のテストや実技のテストを受けるんだ。授業料はほぼタダに近い物 だったし、多くの人が入学したがっていたよ。音楽学校に入って、自分にとって特別だった事はみんな音楽の為だけに その学校に通っていたって事だ。もし普通の学校に通っていたらこうは行かない。ストックホルム周辺の音楽家を志す者、 音楽ビジネスに関わりたい者みんながその学校に通っていた。音楽が共通の言語であって、お金持ちも貧乏人も、 他所からの移住者だろうと関係ない。皆が対等に音楽の事について語り合ったり楽器でセッション出来る。そういう意味では 垣根を越えたコミュニケーションを取る方法を覚えた場所とも言えるね。 環境も非常に良かったと思う。いろんな楽器で色々な人達とバンドを組んでセッションをしたよ。ドラム、ギター、キーボード…。 もちろん歌も歌ったしね。
Dr. Shingo : 小さい頃に夢中になった音楽って何でしたか?
Joel Mull : そうだね、さっき言ったとおりクラフトワークとかを聞いていたかな…母親が「マン・マシン」のアルバムを持っていてね…。
Dr. Shingo : 本当にそんな小さい頃からテクノに興味があったの?
Joel Mull : 本当だよ。確か6歳くらいから聞いていたと思うよ。もちろんロックだって聴いたしね。ジミ・ヘンドリックスやドアーズだって聞いたし アフリカ・バンバーダーみたいなエレクトロとヒップホップが混ざった音楽にも興味があった。だけど音楽学校の仲間達は エレクトロニック・ミュージックを聞いても「そんなの本当の音楽じゃないよ」みたいな事を言ったんだ。プログラムで音楽が 演奏されたり、ドラムマシンの音はもちろん本物のドラムに聞こえない…それで非難する奴も当時はたくさん居たんだよ。 「本物の楽器を演奏しなくちゃ音楽じゃない!」なんてね。
Dr. Shingo : そういう気持ち、楽器を弾いていた経験がある者として非常に理解できますよ。僕もギター一辺倒だった時には テクノは音楽じゃないと思っていたからね。
Joel Mull : だけど自分にとってはギターを録音したりする事と、シンセサイザーで音を作ったりエフェクターを掛けたりする事は同じ事に 思えたんだよ。

Dr. Shingo : なるほどね。ではテクノの何に一番惹かれましたか?
Joel Mull : 多分「音」だと思う。シンセサイズ(合成)された音にあったんだと思う。生の楽器とは違うハーモニーや、周波数がシンセサイザーの つまみをいじる事によって変わったりと自分にとって特別に感じたんだ。そういうシンセサイザーのサウンドスケープの世界に 魅了されちゃったんだろうね。
Dr. Shingo : そういうテクノの「体験」から実際にテクノという音楽を作る、という行為に至ったのは、シンセサイザーで音を作る事に興味が 沸いたからですか? テクノのリスナーだった少年がテクノミュージックを作る様になった経緯を教えて下さい。
Joel Mull : その当時はロックバンドを組んでいて、カシオの玩具から卒業して(笑)ローランドの確か… D-50 というシンセを使っていたんだ。 シーケンサーのプログラムとかも出来るワークステーションと呼ばれる物だった。それがまともに使える初めてのシンセだった。 色々と面白い事がたくさん出来るシンセで、バンドでも色んな音色を試して見たかったのにみんなと来たら「普通のオルガンの音に してくれないか」と来る。それで自分で音を作ってレコーディングしようと思い立ったんだ。普通のラジカセを使って実験的な事を 試みるようになったのもこの頃かな?カセットテープのプレイヤーが二つ付いているラジカセあっただろ?
Dr. Shingo : もちろんテープどおしをダビングする時に使っていましたよ。
Joel Mull : それ。それを使って、片方はただ再生しておくんだ。で、もう一方の録音が出来るデッキの方で録音するんだけど、 途中でリズムに合わせて一時停止ボタンを押すんだ。そうすると途切れ途切れに録音される。それを繰り返して、 後から再生してみるとサンプラーで作ったかのようなブレイクビーツみたいな音楽が出来るんだよ。 そうやってリズムのループを作っていたんだ。子供の頃なんてお金ないからね。工夫して遊んでいたんだよ。
Dr. Shingo : 初めてコンピューターを買ったのは何時でしたか?
Joel Mull : アタリというパソコンだね。 Cubase というソフトで音楽を作っていた。最初の自分のスタジオなんてターンテーブル、ミキサー、 サンプラー、あと手持ちのシンセサイザー。これしかなかったよ。それが94年頃の頃かな?
Dr. Shingo : では90年代のスェーデンの音楽シーンについて聞いてみたいのですが、ジョエルは91年に野外レイブでダンスミュージックと 衝撃的な出会いをしたそうですね?90年代初頭、ストックホルムでテクノをガンガンに掛けているクラブはあったりしましたか? その頃のスェーデンのクラブシーンはどんな感じでした?
Joel Mull : 最初はみんなアシッドハウスだった。89年頃だったかな?だけどその頃はまだ自分は若すぎたからね。 初めて買ったハウスのレコードはインナーシティのアルバムだったっけ…クラブ自体は当時ストックホルムに沢山あった。 だけどテクノが出始めの頃はフライヤーさえないパーティーにうわさで聞きつけて出かけたり、クラブじゃなくて何処か倉庫に サウンドシステムを入れただけの場所でパーティーを行っていたんだ。 その頃が確か16歳頃かな?アダム・ベイヤーやカリ・レケブリッシュと出会ったのもその頃だったね。
Dr. Shingo : 既に彼らはDJを始めていたの?
Joel Mull : アダムは14歳から DJ を始めていた。もちろんキッズ向けのディスコみたいな所が多かったけどね。色々プレイしていたよ。 ヒップホップだってプレイしていた。想像できるかい(笑)?当時は全てが新しかった。 クラブのカルチャーの前にはディスコがあったよね。ディスコではお決まりの曲で盛り上がって、踊り方もツイストやモンキーとか、 何か型が決まった楽しみ方をしていた様に思うけどレイブシーンは違った。 みんな DJ 達は個性的な選曲をしたし皆踊り方だってそれぞれ。なんていうかそれまでのルールを壊したって感じだったね。 音楽シーンだってハシエンダから出てきたハッピーマンデーやストーンローゼーズ、ニューオーダー…色々なジャンルの音楽が 混ざり合っていたし録音の手法だってそれまでとは違う実験的な事が数多く行われた時代だった。 まさしくエレクトロニックミュージックの夜明けだったね。 そして年配の人にとっては、そのムーブメントは恐ろしい物だったと思うよ。自分達が慣れ親しんだ物が新しい 時代のセンスによって塗り替えられていってしまったんだからね。全ての面においてルールが壊されていく時代だったんだ。
Dr. Shingo : 初めてクラブで DJ したときの事を覚えている?
Joel Mull : 93年頃かな?野外レイブのチルアウトブースが初めてのステージだった。ターンテーブルから CD、何でも使って DJ していた。 オーブとかピンクフロイド、タンジェント・ドリームみたいなエクスペリメンタルなトラックを使って DJ していたよ。特殊な方法で レコードを逆回転させたりしたりね…。でもレコードが安定しないから音がうにゃうにゃになっちゃうんだよ。 当時はそういう実験的な音楽にはまっていたんだ。しかもアンビエントルームなら色々プレイ出来るからね。面白かったよ。 ダンスフロアで DJ したのはその後かな?友達のパーティーの手伝いがてらに DJ したんだ。一つ思い出深いのはある友達の 誕生日パーティーをやった事があったんだ。アダムと僕と二人でライブする事になって一生懸命練習したんだ。 彼が DJ して僕がシンセサイザーを即興で弾くんだ。40、50人くらいのパーティーでストロボライト一本しかなくてね(笑)。 あれは面白かったな。
Dr. Shingo : 今それやったらプレミアム・ライブですよ(笑)。
Joel Mull : 93年という年は大きな節目の年だった。僕が始めて EP を出したのもこの年だったしね。アダムやジェスパー(ダルバック)達が 共同で「グローブ・スタジオ」というスタジオを作ったのもこの頃で…今も機能していて今年で14年目になるんだけどね。 初めてのシングルはこのスタジオで作ったんだ。レーベルからプロモーション盤が届かなくてね、自分のデビューEPをレコード屋で 買ったんだけど(笑)。もう本当に嬉しかったよ。「やった〜!レコードデビューだぜ!」ってね。それからはトントン拍子に物事が 進んで、自分達の音楽を世の中に送り出そうと躍起になりだした瞬間でもあり…

Dr. Shingo : ちょっとそこで次の質問に行きましょうか(笑)。今の話に関連する事ですが、95年アダムは自身のレーベル「DRUM CODE」 を立ち上げ、世界からスェーデン産のテクノが注目を集め始めたのもその頃だと思います。当時の日本でもあなた達が世に放った サウンドに大きな衝撃を受けた人達は数知れず、世界中にはスェーデン産のハードテクノから影響を受けたレコードが 次々とリリースされました。当時の事を振り返ってどう思いますか?自分達が一つのムーブメントの中心に居たという感想は?
Joel Mull : 自分達は自身がシーンの中心だった、とは考えないだろうね。アダムに聞いてもカリに聞いてもそう言うだろう。 それが世界でどれだけ影響を与えていたかなんて分からなかったんだ。何しろ自分を含めて仲間内でスゥエーデンの国外に出て DJ している奴なんていなかったから、周りで何が流行っているかなんて分からなかったんだよ。 僕たちは当時まあ言うなればダークなサウンドを好んでいたけど、何て言えば良いのかな…さっきも言った通り、色々なルールが 無い雰囲気だったし何をやっても良いという気持ちだったんだ。 だからああいった物を作れたんだと思うよ。当時のスェディッシュサウンドはちょっとハードめでサウンドは凄く潰れている感じだったね。 そういうサウンドの元を作り上げたのは実はカリ・レケブリッシュだ。彼は僕達に色々と音作りのコツや「マジック」を教えてくれたよ。 カリは間違いなく「スェーデンテクノの父」として語り継がれるだろうね。彼がスェディシュサウンドの基礎を作り上げたといっても過言では ない。では我々はどこから影響を受けたかというと、ベルギーのテクノなんだ。当時のベルギーのサウンドも僕達と同じ様にハードめ だったね。
Dr. Shingo : 僕の印象としては…ジョエルがこの表現が好きかどうか分からないけど…スェディッシュテクノは「ダーティー」な感じがするんだよね。 ベルギーのサウンドがハードと言ったけど、当時のジャーマンテクノもそうだけど両方ともサウンド自体はなんていうか… 澄んでいる感じがするじゃないですか。それに比べるとスェディッシュテクノは…
Joel Mull : なるほど、それは良いポイントだ。カリはね、いつもゲイン(音量)を上げすぎるんだ。
Dr. Shingo : あはははははは!
Joel Mull : 彼はいつもシンプルにしすぎるなとか、もっともっと音量レベルを上げろとか…そういうロック野郎なんだよ(笑)。ゲインメーターが赤色に点滅した 瞬間が一番ホットなんだぜ!ってね。そう、「ダーティー」なサウンドという表現は当たっているね。音が歪むエフェクターを沢山使っていたよ。 だけど当時自分は、というとそこまで曲作りに没頭している訳ではなかった。DJ としてのキャリアを築く方に意識が向いていたんだよ。 その頃一年位ドイツのハンブルグに母親と移住していた時があって、ハンブルグのクラブに通い詰めていたんだ。当時のデトロイトやシカゴからの アメリカ人 DJ や、スベン・フェイト等の有名 DJ が毎週変わり代わりスピンするようなビッグクラブがあってね、自分にとっては DJ の学校みたいな所だった。 僕もたまにロングセットを行ったりしていたよ。…話を戻すと、それは自分達にとっては誇らしい事だよ。自分達はテクノの歴史に1ページを 残す事が出来たわけだしね。で、国内のシーンにそれがフィードバックされたかと言うとそれは難しかった。あるクラブはうまく行っていたし、 全然だめな所もあったしね。結局スェディッシュ・テクノのムーブメントはスェーデンの国外で起きた事だったんだ。実際自分達がスェーデンで DJする事は年に4、5回程度なんだよ。
Dr. Shingo : 本当!?
Joel Mull : 僕達はいつかスェーデンで友達の DJ や世界の音楽シーンを持ち込んで何かをプレゼンしたいと努力し続けてきた。しかしこれが中々 難しくてね…。ラッキーな事に僕達は外国で DJ 出来る環境があるから良いけどね。たまに聞かれるんだ。「おい、スェーデンのシーンは 今どうなってる?」ってね。小さなクラブではここ2、3年うまく行っている事が多いらしいけど…あくまでも小さなクラブでの話だよ。
Dr. Shingo : それはちょっと残念。だけど、いや〜良い話を聞きました。スウェディッシュテクノの基本は「ロックだぜ!」ってね。
Joel Mull : その通り!完全に僕のプロダクションに当てはまる事は無いけれどね。魂はロックだよ(笑)。
Dr. Shingo : ちょっと個人的に感じた事を聞いてみたいのですが、2004年にリリースした「next in line」という EPからプロダクションの傾向が 少し変わりましたね。ジョエル自身の中ではその事についてどう思いますか?
Joel Mull : 確かにその頃からプロダクションというか、自分の音の好みが変わってきた様な気がする。変わろうと努力していた時期でもあるね。 まだ自分の DJ セットの中では雰囲気によってはパンピンなテクノトラックを使う事もあるけど、サウンドプロダクションは反対の 方向に向かっている。テクノの世界全体的に見ても、4年前から大きな変化が訪れたと感じるようになった。みんな昔のハードミニマルの 時代のようにパーカッションを入れなくなったし、ミニマルテクノが生まれた時代に逆戻りしている気がするよ。 「next in line」 が 現在の自分のプロダクションに通ずる「入口」の様な作品だった事は確かだね。
Dr. Shingo : そして現在の 「UnderWater」 からのリリースや、4月以降に控えている 「HartHouse」 からのアルバムリリースに繋がって行きますが、 自分自身が作り上げてきたサウンドを自分で壊していく事、前に進む事は大変だと感じますか?一度、作り上げたサウンドがあると そこにハマってしまって抜け出せないアーティストも数多くいますが…。
Joel Mull : 僕の場合は、買ってきた新しいレコードからインスピレーションを受ける場合が多いし、一つの事にハマってそれをやり続ける事が苦手 なんだよ。どうやら僕に良いビジネスマンになる素質はなさそうで、これが売れたからこれをやり続けようとか、こういうブランディングを しようとか、そういう事が出来ないんだ。いつも自分に正直にトラックをプロデュースしてきたつもりだよ。その分、リリースをする時には 凄く迷うけどね。自分の曲にいつも確信が持てないんだよ。だから自分のレーベルからリリースするよりも人のレーベルからリリースする方が 楽だと感じる。他人にジャッジしてもらう方が楽なんだよ。それでダレン(エマーソン)に会ったときや、シャロン (HartHouse のオーナー) にトラックを渡した。彼らが「いいじゃん。ウチでリリースしようか。」そういってくれればそれでOK。いつもそんな感じさ。それに今回はこのレーベル、 次回はこのレーベルと、僕の曲が色々な人の手に渡り、色んなディストリビューションを通して世界中の人に渡れば良いプロモーションにも なるだろう?それはすなわち自分の環境を常に進化させて行っている事にも繋がると思うんだ。とにかく一つの場所にスタック(ハマる)事だけは したくない。それに尽きるよ。
Dr. Shingo : もし若い音楽プロデューサーにアドバイスをするとすればどんな事でしょう?
Joel Mull : コピーをするな、自分の道を歩む事。自分自身を信じて良い曲が出来たら自分自身でしっかりプロモーションをする事だ。 今はマイスペースや色々な手段があるんだからね。他人がやってくれるかも、何てことは当てにしない事。そしてルールを破る事だ。
Dr. Shingo : 長いインタビューでしたが本当にありがとう!日本のファンにメッセージをお願いします!
Joel Mull : keep on smiling and enjyoy your life! ARIGATOU !!
End of the interview
Dr.SHINGO プロフィール
長野県出身。幼少から様々な楽器を演奏し、米国・バークリー音楽院への留学を経て2001年よりデモテープの配布を開始、最終的に故 christian morgenstern のレーベ ル Forte Records よりアルバムリリースのオファーを受ける。2002年デビューシングル「Have you ever seen the blue comet?」でワールドデビューを皮切りにアルバム「Dr Shingo's Space Odd-yssey」をリリースし、一躍その名を世界に轟かす。Sven Vath、石野卓球、等のトップアーティストからも絶大な評価を得、世界各国からリミックスの依頼が舞い込むようになる。 2004年5月にはセカンド・アルバム「ECLIPSE」をドイツの TELEVISION RECORDS よりリ リース (日本盤は先行で3月にMUSIC MINE よりリリース)。約2年間の活動の中で20枚ものシングル、アルバム、リミックスワーク、そしてコンピレーションCDへの楽曲提供を果たし、名実共に日本を代表するエレクトリックミュージック・プロデューサーへ と成長した。幅広い音楽の知識を持ち、それを余す所無く自身のプロダクションに応用する事により、実験的であり、斬新なトラックを発表、常に現在のテクノシーンを前進させようとする姿勢を崩すことは無い。特に類を見ない抜群のメロディセンスが彼のプロダクションに更なる“ポップ”なエッセンスを加えている事により、孤高のエレクトリックミュージックを発信し続けている。
バックナンバー
連載第9回 : Closing
2006
連載第8回 : Interview with Zombie Nation
連載第7回 : Interview with Dave DK
連載第6回 : 春のお知らせ
連載第5回 : Interview with Frank Lorber
連載第4回 : 青山 Maniac Love
連載第3回 : Interview with Domink Eulberg
連載第2回 : Interview with Maral Salmassi
連載第1回 : Interview with Monika Kruze